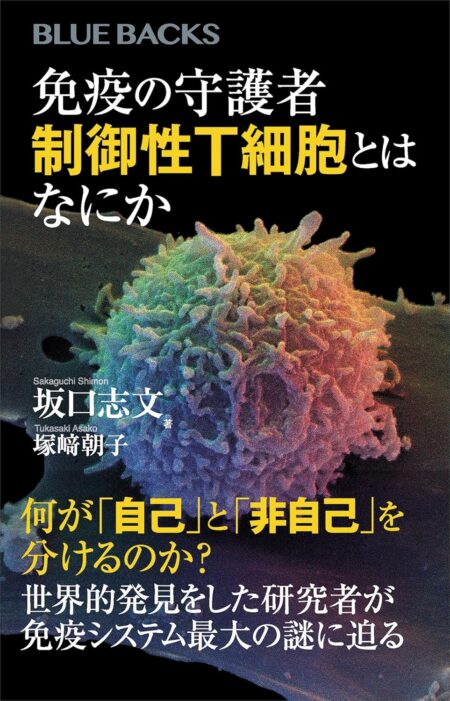免疫系における「自己」と「非自己」の境界は曖昧で、誰もが自己免疫疾患を発症する可能性がある。「自己」に対する免疫不応答のことを免疫自己寛容という。免疫自己寛容の維持に中心的役割を果たしている生体内の免疫細胞を捉えて、制御性T細胞と命名した。この細胞は、免疫系の”守護者”として、その暴走を抑えるように働いている。
ヒトはなぜ病気になるのか
ヒトはなぜ病気にならずにすむのか
* 免疫系の「正の応答」
体内に異物(病原体など)が侵入してきても、それらを排除することにより生体は防御される。体内に生じたがん細胞を排除するのも同様な働きである。
* 免疫系の「負の応答」
ヒトの免疫系には過剰な免疫反応を起こさないようにする働きが備わっている。飲食によって取り込まれる「食物」や妊娠中の「胎児」も、私たちの体にとっては「異物」である。これらに過剰に反応しては、さまざまな不都合が生じてしまう。
急増する自己免疫疾患
免疫系は「正の応答」と「負の応答」との微妙な均衡によって成り立っており、バランスが崩れると「不都合」が生じる。その代表にアレルギー反応がある。
花粉症
スギなどの花粉が鼻の粘膜内に入ると、抗原提示細胞の一つである樹状細胞がこれを異物(抗原)として認識する。その抗原の情報は、免疫細胞の中でも、白血球の一種であるリンパ球のT細胞へと送られる。T細胞からさらに、別のリンパ球であるB細胞に情報が送られると、花粉にピタリと合う「抗体」(スギ花粉特異的IgE抗体)が作られる(感作が成立)。このIgE抗体が、抗原である花粉を再び捉えると、鼻の粘膜下組織にある肥満細胞から、炎症を起こす物質(ヒスタミンやロイコトリエン)が放出される。この結果、ヒトはくしゃみ、鼻水、鼻づまり、かゆみなどに悩まされる。
炎症性腸疾患:潰瘍性大腸炎、クローン病
腸や大腸などの消化管に炎症が生じて、粘膜がただれて潰瘍ができる病気である。
主な症状は、下痢や血便、腹痛、発熱、貧血などである。症状の軽減または消失(寛解)と、再燃を繰り返し、厚生労働省の特定疾患(難病)に指定されている。
腸内の免疫細胞は「負の応答」によって制御されており、有益である異物に対して過度に反応することがないようになっている。しかし、免疫系のバランスが崩れると、自己の腸内細菌に対しても過剰な反応を起こすようになり、炎症性腸疾患を発症する。
自己免疫疾患
異物をきっかけとして起こる病気とは別次元の病気で、免疫細胞が「自己」の組織や細胞を異物と見なして、攻撃してしまうことで発症する病気である。多様な種類があり、人口の5%が何らかの自己免疫疾患に罹っているといわれる。
関節リウマチ
免疫系が、関節の滑膜という組織を攻撃することで起こる疾患。
1型糖尿病(インスリン依存型糖尿病)
免疫系が、インスリンを分泌している膵臓のβ細胞を攻撃することで起こる。
多発性硬化症
中枢神経(脳、脊髄、視神経)に繰り返し炎症が生じる疾患。若年者に多い。これも免疫系の暴走が原因である。
全身性エリテマトーデス(SLE)
特定の臓器だけでなく全身に免疫系が攻撃を仕掛けてくるため、全身に症状が出る自己免疫疾患である。発熱、倦怠感に加え、関節・皮膚・腎臓・肺・中枢神経等さまざまな臓器異常が起きる。
臓器特異的自己免疫疾患
1型糖尿病、多発性硬化症など
全身性自己免疫疾患
関節リウマチ、全身性エリテマトーデスなど
自己を攻撃する細胞を誰もが持っている
何かのきっかけでこの免疫細胞が暴走するようになれば、誰でも自己免疫疾患を発症する可能性がある。自分を攻撃する免疫細胞は、何かのきっかけにより、容易にかつ強力に誘導される。
しかし、実際には95%近い人は自己免疫疾患を発症せずにすんでいる。「自己」と「非自己」の境界が揺らいでいて、本来攻撃しない「自己」を攻撃対象にしてしまう5%の人に自己免疫疾患が起きると考えられる。
「自己」「非自己」は連続的
1980年代初頭、胸腺で作られるリンパ球(T細胞)の中から、それまで知らされていなかった免疫系の暴走を抑える細胞の存在を探り当て制御性T細胞(Tレグ)と命名した。制御性T細胞は、正常な個体(健常人)の血液中のCD4陽性T細胞の約10%(リンパ球全体の5%)を占めている。
私たちの体内に備わっている免疫細胞の中には、「自己」に過剰に反応して攻撃するT細胞もある。こうした細胞は自己免疫疾患を引き起こしかねない厄介者である。一方、T細胞の中には、免疫細胞そのものを抑制する機能を持ったT細胞(制御性T細胞)もあり、免疫系は両者によってバランスをとることで恒常性を維持しており、病気が頭を出さないようになっている。
幻となったサプレッサーT細胞
「免疫反応を抑える免疫細胞」の概念は、制御性T細胞を発見する少し前から提唱されていた。1970年代に華々しく登場したのが、「抑制性T細胞(サプレッサーT細胞)」と名付けられた細胞が存在するという仮説だった。客観的に実体を示せなかったために、その存在は程なくして否定されることとなった。今では、”なかったもの”とみなされている。
制御性T細胞は、分子生物学的には、サプレッサーT細胞と全くの別物だあるが、混同されたことで、日の目を見るまでに長らく足踏みをすることになった。しかし、世の中の目が向いていなかったことで、重要な研究成果はほぼ独占することができた。
FoxP3遺伝子を発見
2003年、制御性T細胞の発生、機能発現、分化状態の維持、それらのすべてを制御しているマスター遺伝子が、FoxP3であることを発見した。FoxP3は、細胞分化を発動する指令スイッチのような機能を持つマスター遺伝子であり、制御性T細胞の機能に関わる特定の遺伝子セットを発現させる機能を持っていた。
免疫の恒常性の維持
臓器移植の拒絶反応(移植免疫)、炎症、アレルギー反応、さらには妊娠においても、制御性T細胞は、さまざまな有害で過剰な免疫反応を抑制する。
一方、制御性T細胞は、がん細胞に対する免疫反応を抑制することにより、腫瘍の増殖に関わっていることも解明されてきた。
がんの免疫治療
制御性T細胞を使った治療として、熱い期待を集めているのが、がん治療への応用である。がん組織には、制御性T細胞が過剰に浸潤していることがわかっており、それを踏まえた免疫治療が鍵になってくる。
がんの免疫療法においては、”自己もどき”のがん細胞に対する免疫応答を上げなくてはならず、そのためには免疫を抑制しようとする体内のの制御性T細胞を減らす必要がある。
気を付けなくてはならないのは、免疫系を抑える制御性T細胞を完全に取り除いてしまうと、自己免疫疾患を発症してしまう。どの程度まで制御性T細胞をを減らせば、副作用としての自己免疫疾患を起こさずに、がん細胞を攻撃させられるのかを知ることだ。
胸腺に潜む未知なるT細胞
1969年、愛知がんセンター研究所の西塚康章先生と坂倉照妤先生が、生まれて間もない(生後2〜4日の間に)雌マウスから胸腺を摘出すると、成長後に卵巣の萎縮が起こることを報告。
謎の臓器「胸腺」
西塚先生が胸腺摘出マウスが自己免疫疾患を発症することを示唆する論文を発表した当時、まだ胸腺の働きははっきりわかっていなかった。
オーストラリア人科学者ミラーは、胸腺が免疫反応と不可分の拒絶反応を引き起こす免疫細胞を産生し、成熟させる器官であることを発見した。このリンパ球を胸腺依存性リンパ球と名付けた。
クローン選択説
オーストラリアのウイルス学者バーネットが提唱
一種類ずつの抗体を産生するリンパ球があらかじめ多数用意されており、病原菌などの抗原が侵入すると、それと対応する抗体分子を受容体として持つリンパ球(B細胞)が選択され、それが増殖して同種のリンパ球の集団(クローン)が作られるという説。
我々の体内で骨髄細胞(造血幹細胞)が分化して免疫細胞が作られる過程において、外界の作用とは無関係に、無数の抗原に特異的に反応する細胞(抗体産生細胞)がランダムに作られる。一つの細胞は特定の抗原に特異的な一種類の抗体だけを作り、その細胞の一群はクローンになる。
免疫系の応答:「自然免疫」と「獲得免疫」
自然免疫
異物を貪食するマクロファージなどの細胞が中心になって働く。
獲得免疫
異物(非自己)を認識して抗原特異的に応答し、T細胞やB細胞などのリンパ球が中心。
細胞性免疫
主にT細胞が担う局所的な免疫反応。1型ヘルパーT細胞が抗原を認識すると、細胞傷害性T細胞(キラーT細胞)が活性化されて、病原体(異物)に感染した異常細胞を攻撃する。
液性免疫
B細胞が攻撃の主役。2型ヘルパーT細胞がサイトカインを産生すると、B細胞が形質細胞(抗体産生細胞)へと分化して、B細胞から産生された大量の抗体が体液を介して全身に広がる。
制御性T細胞の目印を追い求めて
CD4陽性T細胞
病原体を攻撃するB細胞を選択的に活性化し、抗体を作らせる機能を持つことから、ヘルパーT細胞と呼ばれる。
フローサイトメーター
この機器を使えば、モノクローナル抗体と抗原抗体反応を起こさせることで、リンパ球をCD抗原ごとに自動的に分類できる。
CD4(ヘルパーT細胞に発現)、CD8(キラーT細胞に発現)
CD25陽性CD4陽性T細胞
免疫系に少数ながら存在するCD25陽性CD4陽性T細胞は、制御性T細胞(以下、Tレグ)と命名。CD25陽性CD4陽性T細胞は、最大でも末梢組織のCD4陽性T細胞の10%を占めるにすぎない。このわずかなリンパ球を取り除いただけで、自己免疫疾患という重い病気が起こってくる。
免疫自己寛容
1995年頃は、CD25こそは、Tレグの最も信頼性の高いマーカーだと考えられていた。正常マウスの末梢組織のヘルパーT細胞(CD4陽性T細胞)のうち、CD25陽性T細胞はたかだか5〜10%を占めるにすぎない。にもかかわらず、そのCD25陽性T細胞を除去するだけで、さまざまな自己免疫疾患を誘導することができたからだ。
正常な胸腺は、T細胞の表面にCD25分子とCD4分子を共に発現した「CD25陽性CD4陽性T細胞(Tレグ)」を機能的に成熟した状態で常時生産している。
Tレグは、やみくもに免疫応答を抑制しているのではなく、生体内の状況を何らかの方法で察知して、自分の組織や器官を攻撃しない「免疫自己寛容」の状態を作り出している。
自己免疫疾患などの免疫系の暴走を食い止めるための防護手段
① 胸腺における自己反応性T細胞の排除・・・・[ 壊す ]
遺伝子には、「過激なT細胞」は自動的に自死するようなプログラムが仕組まれている。これは、胸腺におけるT細胞の「負の選択(ネガティブ・セレクション)」と呼ばれる。最終的にある程度の強さで反応するT細胞クローンだけが選抜され、「正の選択(ポジティブ・セレクション)」という。
② 自己反応性T細胞の不活化(免疫不応答)・・[ 黙らせる ]
①の防御網をすり抜けてしまう自己反応性T細胞が存在する。そこで、二番目の防衛ラインとなるのが、血管とリンパ管である。
③ Tレグによる抑制・・・・・・・・・・・・・[ 押さえ込む ]
①と②の防御機構をもってしても、すべての自己反応性T細胞を排除しきれない。このTレグによる積極的な防御が最も重要と考えられている。
Fox p3遺伝子の発見
Fox p3遺伝子のmRNAは、正常マウスの末梢組織のCD25陽性細胞のみに検出された。「Fox p3は、Tレグに特異的に発現する遺伝子で、Tレグの分化を制御する遺伝子と証明された。
Fox p3を導入した細胞は、Tレグ(CD25陽性CD4陽性T細胞)と同様に、通常のT細胞の増殖を顕著に抑制し、免疫反応を促すサイトカイン(IL-2、IL-4、IL-10、IFN-γ)の生産を抑制した。
ヒトの病気もTレグの異常が原因
かつて、自己免疫疾患は、標的となる臓器に異常が起きたために生じてくると考えられていた。そうでなく、「免疫系のほうに異常があって、どこが傷害を受けるかは、その人の免疫応答性、特に遺伝的な背景による。」というのが、1980年から提唱していた仮説が証明された。
Tレグが免疫を抑制するメカニズム
骨髄で生成されたT細胞前駆細胞は胸腺へと移動し、厳しい選別を受ける。自己の細胞との親和性が高く、自らを攻撃するT細胞は「負の選択」によって、積極的な細胞死(アポトーシス)に追い込まれる。自己の細胞との親和性が低く、自己に対する攻撃性が低いT細胞は「正の選択」を受けて、末梢組織に移動してナイーブT細胞となる。自己の細胞との親和性が中間的で、自己の細胞に対してほどほど反応するT細胞がTレグとなる。
Tレグは、さまざまな手段を用いて未熟なナイーブ細胞に働きかけ、エフェクターT細胞へと変化しないようにブレーキをかける。こうして、「免疫自己寛容」を実現している。
Tレグの免疫抑制の方法
① サイトカイン等の化学物質を用いた、細胞間接触を伴わない免疫抑制
中心となるのは、IL-2の制御。
② 細胞表面に発現する補助刺激分子を使った細胞間接触を伴う免疫抑制
中心はCTLA-4の制御により発揮。CTLA-4は「免疫チェックポイント分子」の一つ。
まとめると、Tレグは、免疫応答に必須のサイトカイン(IL-2)の枯渇化によって免疫抑制を図るというアプローチに加えて、CTLA-4のような細胞間接触による免疫抑制によって標的とするT細胞の働きを抑制することができる。
制御性T細胞でがんに挑む
がんを監視している免疫機構
Tレグを応用した医療として、ヒトで最初に実用化されるのは、がんの免疫治療だろうと考えられている。
20世紀に入り、エールリッヒが「体内では絶え間なく異常細胞(がん細胞)が出現しているが、免疫系が排除して生体を防御している」という概念を提唱した。
がん細胞は非自己でなく自己である
がん細胞に対する「腫瘍免疫」とは、ある意味で「自己免疫」だと捉えるのが妥当である。免疫療法では、がん細胞を「非自己」と見なすのではなく、「自己」の抗原に対する免疫応答によって排除する方法を考慮すべきである。
がん細胞は、”自己もどき”細胞であり、「自己免疫」によってしか増殖を抑制できない。
がん患者の血液中や腫瘍内部では、活性化したTレグが異常に増加している。
免疫チェックポイント阻害薬
〜 Tレグに関わりのある細胞表面分子を標的として狙い撃つ 〜
ヒトのがんでは、乳がん、肝臓がん、膵臓がん、消化器がん、悪性黒色腫(メラノーマ)などで、腫瘍局所におけるTレグの増加が認められている。
いかにTレグをコントロールし、その免疫を解除するかが重要である。Tレグを過剰に除去すると、自己免疫疾患などを発症する危険性を伴うため、注意を払わなくてはならない。
免疫チェックポイント分子
〜 責任分子としてのCTLA-4 〜
CTLA-4は、活性化T細胞だけではなくTレグの表面に恒常的に発現している補助刺激分子であり、抗原提示細胞の表面に発現するCD80やCD86と結合することにより免疫を抑制する機構が発動する。
2003年にヒト型抗CTLA-4抗体の有効性が示され、2011年にイピリマブが実用化された。
〜 本庶佑氏が発見したPD-1と呼ばれる分子 〜
PD-1は、活性化した免疫細胞に広く発現しており、免疫応答を抑制する機能を持つことが証明された。特に腫瘍内ではPD-1がが高発現している。
抗PD-1抗体のニボルマブ(オプジーボ)も、免疫チェックポイント阻害薬として開発された。
近年、ニボルマブの投与によって急速に腫瘍が増大し、病勢進行を示す患者が報告されている。胃がん患者の10〜30%がHPDを発症していた。
イピリムマブを投与されたメラノーマ患者では、腫瘍が消えたのと同時に、「脱色素症」が生じて、毛髪や眉毛、まつ毛が白くなってしまうことがある。自己免疫と腫瘍免疫はリンクしており、がんを攻撃した細胞傷害性T細胞が、正常なメラノサイトをも破壊してしまったためだとみられている。
Tレグを操作するがん治療
腫瘍内に浸潤するTレグを除去することにより、キラーT細胞の抗腫瘍免疫応答が活性化される。Tレグを除去するために、オンタック(デニロイキン・ディフティトックス)という薬を用いた臨床応用も進められている。オンタックは、CD25陽性の皮膚T細胞リンパ腫の治療薬である。オンタック投与でTレグの数を減らせるのだ。
慢性リンパ性白血病患者において、フルダラビン(フルダラ)がTレグの割合を低下させることも示された。
ATL治療薬として、CCR4を認識して結合する抗CCR4抗体が開発されている。モガムリズマブ(ポテリジオ)である。これをATL患者に投与すると、CCR4陽性の白血病細胞(ATL細胞)を攻撃して、顕著な延命効果がある。さらに、Tレグを減らす効果があることも認められている。
制御性T細胞が拓く新たな免疫医療
制御性T細胞(以下Tレグ)の臨床への応用は、がん治療だけではなく、臓器移植の際の拒絶反応の制御、自己免疫疾患、感染症、アレルギー疾患の治療など、多種多様な疾患や症状への対応が考えられている。Tレグの作用を弱めたり強めたりすることができれば、がんや感染症などでは免疫反応を増強し、自己免疫疾患やアレルギー疾患では免疫反応を抑制することで病気を治療できる。
移植免疫
臓器移植の成否は、急性期・慢性期の拒絶反応をいかにコントロールできるかにかかっている。
移植後概ね3ヶ月で起こる急性期拒絶反応の主役は、細胞傷害性T細胞(キラー細胞)である。
例えば腎臓が移植されると、そこから遊離した抗原タンパク質を樹状細胞やマクロファージが見つけて、異物の侵入を免疫の司令塔であるヘルパーT細胞に伝える。その情報を得たヘルパーT細胞は、異物を破壊するキラーT細胞を動員して、移植された腎臓に侵入させて攻撃させようとする。
一方、臓器が生着して、病状が比較的安定してくる慢性期に起こる拒絶反応の主役は、B細胞である。
3ヶ月を超えた慢性期では、ヘルパーT細胞がB細胞に抗体を作るように促す。B細胞からミサイルのように放出された抗体は、移植された腎臓の血管に取り付いて、これを破壊しようとする。
自己免疫疾患
Tレグの活性を高めることは、自己免疫疾患の治療に結び付く。活性化T細胞をできる限り除去し、抗原特異的なTレグを強化して移入できれば、自己免疫疾患の新しい治療法が可能になる。
免疫反応を抑えるだけの治療薬
第一世代の免疫抑制薬
増殖しているリンパ球を減少させる細胞傷害性の薬剤。
代謝拮抗薬(メソトレキセートなど)、アルキル化薬(シクロホスファミド)など
第二世代の免疫抑制薬
リンパ球の活性化と増殖に関わるリンパ球の細胞内シグナル伝達物質を阻害する薬で、IL-2の産生を特異的に抑制し、T細胞の活性化を抑える。
シクロスポリン、タクロリムス(プログラフ)、ラバマイシン(シロリムス)など
第三世代の免疫抑制薬
Tレグを増やすような薬を免疫抑制に使う。低用量のIL-2は、Tレグだけを選択的に増やす。
新型コロナウイルスとTレグの働き
COVID-19は高齢者で悪化する傾向が見られているが、加齢に伴って免疫を担うリンパ球の反応性が落ちる半面、Tレグは増加してくるので、高齢者の免疫反応が抑え気味になる。
COVID-19が重症化した結果として、サイトカインストーム(急激な免疫の暴走)が起きると、致命的になることが知られている。慢性的な炎症反応であれば、Tレグは免疫の行き過ぎを抑えて鎮静化し、バランスを保つ方向へと持っていくことができる。しかし、サイトカインストームのような急性期の炎症の場合、Tレグはその場に駆け付けはしても、多勢に無勢で、力負けしてしまい、暴走を抑えることができない。一気にサイトカインを中和できる抗IL-6抗体(トシリズマブ)のような薬剤が極めて有効だろう。
Tレグは一定割合に保たれる
Tレグは、どんな人でもCD4陽性T細胞の10%内外に保たれている。Tレグが少ない人は、よくいえば、免疫反応がちょっと高いので、がんになりにくいともいえるし、アレルギーなどにはなりやすいといえるのかもしれない。
高齢になるとTレグはやや増えることが知られている。
坂口 志文
日本の免疫学者、医師。大阪大学栄誉教授・免疫学フロンティア研究センター特任教授、京都大学名誉教授。ベンチャー企業レグセルの創業者。2025年に「末梢性免疫寛容に関する発見」により、メアリー・E・ブランコウ、フレッド・ラムズデルとともにノーベル生理学・医学賞を受賞した。