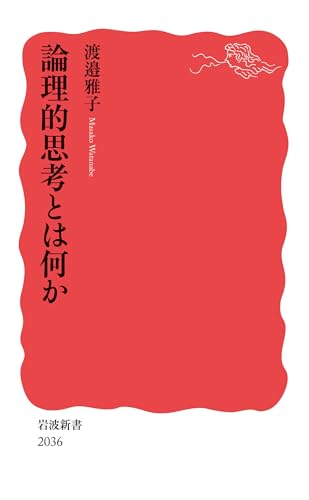はじめに 〜 論理的思考はひとつなのか 〜
・形式論理:論理的思考が世界共通で不変という考えのもとになった論理学
・本質論理:論理には文化的側面があり、それを価値観に紐づける論理学
多元的思考:複数ある論理的思考を、目的に応じて選択的に使いこなすこと。
論理的思考はグローバルに共通なものではなく、実は文化によって異なっており、それぞれの教育の過程で身につけていくものである。論理的思考の型は、それぞれの社会が何を重視し文化の中心に据えるのかと深く関わっている。
序章 西洋の思考パターン 〜 四つの論理 〜
① 論理学、② レトリック、③ 科学、④ 哲学
論理学の論理
論理的であること=矛盾のないこと
論理学の根幹をなすのは、「矛盾を排除して無矛盾を維持すること」である。
誰もがその結論を受け入れる普遍的なものでその中間は考えない。
論理学の推論 〜 演繹的推論と三段論法 〜
演繹する
一般的、普遍的に正しいとされる大前提から、個別具体的な結論を得ること。
三段論法
正しいとされる大前提と小前提の二つの前提から一つの結論を導き出す。
「全てにAはBである。」そして「CはAである。」→「よってCはBである。」
説得(レトリック)の論理
レトリックとは何か
レトリックの目的は、人を説得することである。レトリックは、常識を基盤として、一般大衆に向けて説得的な弁論を行うための技術である。
蓋然的推論
人々の常識を前提とした、常ではないが、多くの場合に正しい推論。
演繹
一般的・普遍的な前提から個別・特殊な結論を得る方法。
帰納
具体的なことがらから一般的に通用する原理や法則を引き出す推論の方法。
レトリックは、人を説得する技術であるので、「理性(ロゴス)による論理的な説得」のみならず、話し手の「倫理(エトス)」と受け手の「感情(パドス)」をも視野に入れている。
説得するとは
説得するとは、受け手の心からの同意を引き出し、言論によって受け手の考えや行動を変えることである。圧力や権威によって強制的に同意を引き出すのは説得と言わず、受け手が自発的に賛同して考えを変えることを指す。
日常の論理
レトリックにおいて重要なのは「日常の論理」である。私たち人間は何もないところから自由に考えているわけではなく、使い慣れた型を用いて議論したり人を説得したりする。
蓋然的
必然的の対義語であり、ある程度確実なこと。
例証
具体的な事例からそれに類似した他の事例に移行して主張を根拠づける。
レトリックにおける論理的な思考とは、「説得」という目的を達成するための戦略的な思考といえる。
科学的発見の論理
アブダクション
アブダクションは遡及(そきゅう)的推論とも呼ばれ、結果からさかのぼってその原因を推測する論理である。
探求の第一段階
その事実がなぜ起こったかについて可能な説明を与えてくれる仮説を考え出す。
探求の第二段階
「演繹」によって行われる。仮説に含まれている予測を、実験や観察で検証(テスト)できる形に、言葉または数式で示さなければならず、仮説を解明し、証明できる形にする段階である。
探求の第三段階
「帰納」によって行われる。結論がどれだけ経験と一致するのかを確かめる「帰納」の段階に入る。経験に照らして判断するのが帰納の思考である。
例)海王星の発見
非論理的な思考が、未知のものの発見という思考の飛躍を可能にする。科学という厳密な学問領域とは一見相容れないような「創造性」を積極的に受け入れる推論の形がアブダクションである。レトリックとは異なり、これまでの通念や常識の覆いを取り去ったところに、既存のものの新しい関係を見出し、そこから「新たな観点 = 発見」を導き出す。
帰納との違いは、帰納は観察可能な事象を一般化するのに対して、アブダクションは多くの場合、観察可能な事象から直接観察することが不可能な原因を推論することである。
イノベーション(革新)を起こす思考法
これまでに見られなかった新たな背景や原理を、その原因にさかのぼってアブダクティブに推論し突きとめることをビジネスコンサルタントはすすめている。
21世紀、人工知能の研究者たちは、論理学が切り捨ててきた「厳密でない推論」に人間独特の性質を認め、アブダクションの「ものごとを結びつけ創造する」思考法を積極的に研究に取り入れている。
アブダクションの思考法の特徴
1) 驚くべき現象の原因究明は、「なぜ」に答える目的志向に行われるということ。
2) 「もし・・ならば・・である」という「そうらしい」ことから出発して知識の拡張を目指すこと。
可謬(かびゅう)主義:常に誤りが見つけられ修正される可能性を残しておかなければならない。誤りを正す作業の蓄積によって知識は広がる。
3) 「解釈」が変わることによって、ものの見え方や考え方が激変する。
哲学的探求の論理
哲学の思考法
議論が噛み合わないのは、異なる前提(定義・想定)から推論しているためで、推論そのものが間違っているわけではないことも多々ある。哲学の目的は物事の本質を捉えることである。できるかぎり共通の了解にたどり着き、それを土台に議論して対立を解消したり、問題解決したりすることが哲学の意義である。哲学が扱うのは「考え」という分野である。
弁証法:ドイツの哲学者ヘーゲルの弁証法
ある見方、それに対する見方、それらを総合する見方という[ 正→反→合 ]の段階を経ることによって、概念が自己内の矛盾を解決して高次の段階へ至る論理構造を提示する。
論理学は「正しい前提」から出発して正しい結論を導くが、哲学は私たちが正しいと考えている「前提」とはどのようなものかを問う。
第一章 論理的思考の文化的側面
何が「論理的」だと感じさせるのか
論理的であることは、社会的な合意の上に成り立っている。だから、文化圏によって違いが現れる。論理的であること=読み手にとって記述に必要な要素が読み手の期待する順番に並んでいることから生まれる感覚である→論理的であることは社会的な合意の上に成り立っている。
論理と合理性
論理的に思考することと、合理的に行動することは連動している。
合理性:「形式合理性」「実質合理性」
実質合理性
- 「何が行為を決断するに値する価値を持つ目的なのか」という目的の判断に関する合理性。
- 特定の理念・理想を達成しようとする。
- 目的達成の過程となる「行為そのもの」に価値を置く。
形式合理性
- 決定済みの目的に対して、最も効率的な手段、理論上確実な手段を選択する合理性。
- 手段を計算や法則・規則を通用して技術的・道具的に選択する。
- 行為の結果を重視する。
集団間の衝突はなぜ起こるのか
葛藤の原因は、「実質合理性」と「形式合理性」の違いによると考えた。
形式合理性における手段選択の計算可能性と効率性は、実質合理性の博愛や平等などの価値の重視との間に強い緊張関係を生み、これら二つの異なる合理性を用いる社会や共同体の間に和解し難い対立を生む。
経済・政治・法技術・社会のそれぞれの論理
合理性に関する二つの指標〜形式・実質、客観的・主観的〜からなる四つの領域の特徴
1) 経済領域(形式合理性による主観的判断)・・・アメリカ
2) 政治領域(実質合理性による客観的判断)・・・フランス
3) 法技術領域(形式合理性による客観的判断)・・イラン
4) 社会領域(実質合理性による主観的判断)・・・日本
第二章 「作文の型」と「論理の型」を決める暗黙の規範
経済の論理〜アメリカのエッセイと効率性・確実な目的の達成
経済領域は、効率的に最大限の収益を上げることを目的とする。経済領域のレトリックは「効率的か否か」が主導的な観点となる。
五パラグラフ・エッセイの構造と論理
エッセイの型
序論 主張:結論となる主張
本論 主張を支持する三つの根拠(事実)
結論 主張を別の言葉で繰り返す
演繹的な書き方 〜最重要から具体へ
主題掲示文が最初に現れるものを「演繹的」作文と呼び、最後に置かれるものを「帰納的」作文と呼ぶ。常に結果からさかのぼって手段を決定する「逆向き設計」で思考することが基本。
エッセイ
エッセイは、「前提」となる主張が最初にぽんと置かれて、そこから具体的事実を判断する演繹に似た形をとる。
エッセイの論証の適切さは、「信頼性」と「妥当性」が引き合いに出される。
信頼性:主張を支持する事実/情報に誰でもアクセスして確認できること
妥当性:事実/情報が確かに主張をサポートしていること
アメリカにおける現代レトリック(作文法)
書き手の目的に合致した書き方を選択することが、「良い作文」の条件。
「大衆民主主義的」かつ「経済効率性」に優れた独自の書き方と思考法である。
結論を先に述べ事実で論証するエッセイの型は、文化的な慣習の影響を受けにくく、言語の違いによる表現法の影響も受けにくい。
エッセイの型は経済のグローバル化が加速した二十世紀の終わり頃から、ビジネスにおける世界標準のコミュニケーションの型ともなっている。
政治の論理 〜フランスのディセルタシオンと矛盾の解決・公共の福祉
政治領域のレトリックは、「十分な審議が行われたか否か」が重要な観点となる。「責務の倫理」が意思決定の流儀とされる。この責務の精神は、すべての政治的な目的を達成するために必要不可欠なものとされている。
ディセルタシオンの構造と論理
「ディセルタシオン」と呼ばれるフランス式小論文は、弁証法を基本構造とする。
弁証法
論ずべき主題に対する「一般的な見方」、「それに反する見方」、「それらを総合する見方」を「正ー反ー合」の構成に位置付けて、「正」と「反」の矛盾を「合」で解決する。弁証法では、これら三つの見方を検討する「過程」そのものが重視される。
ディセルタシオンの型
導入 ① 主題に関わる「概念の定義」
② 「問題提起」→ディセルタシオンの肝となる部分で「問い」の形にして表明
③ 正ー反ー合を導く「三つの問い」による全体構成の提示
展開 弁証法:a 定立(正)、b 反定立(反)、c 総合(合)
結論 ① 全体の議論のまとめ
② 結論
③ 次の弁証法を導く問い
a 定立:「正」の部分。一般的に受け入れられている考えを論証する。著名な哲学者の論理を引用して論拠を例証する。
b 反定立:「反」の部分。終わりに「合」への移行を暗示するさらなる問いを提示する。
c 総合:「正」と「反」の議論を総合する主張を引き出すための問いを提示し、その答えとして、「合」の主張を提示する。
論理を支える「論証の基本ブロック」
「主張+論証+例証」の三要素からなる。
「正」「反」「合」それぞれの視点は、通常三つの論拠とそれぞれの例証(引用)によって論証される。三つの視点それぞれに三つの論拠、それら三つの論拠それぞれに対して三つの引用がある。
ディセルタシオンにおいては、「私がどう考えるか/感じるか」という書き手個人の意見や体験、感情は全く意味を持たない。政治領域においては、個人の利益よりも公共の利益を優先させる政治理念を理解し、日常の判断や実際の行動に結び付けられる能力が必要とされる。
ソクラテスの産婆法
問いを立てて相手に答えさせ、さらなる問いによって相手の答えの矛盾に自ら気づかせることによって、それまでの考えを捨てさせて探求を進める方法である。
ディセルタシオンでは、「正ー反ー合」を導く三つの問いに答えていくことで、書き手に一人でソクラテスの産婆法の過程をたどらせる。
法技術の論理 〜イランのエンシャーと真理の保持
法技術のレトリックにおいては、「真理か否か」が重要な観点となる。「結論(答え)が一義的(ひとつ)に決まること」が重要である。
[ 三段論法 ]
真実である大前提から始めて小前提で具体的事例を取り上げ、大前提で示された真の関係を具体的事例にあてはめることで、既知である真のことがらから未知のことがらが真であることを推測する。「形式の正しさ」が議論の正しさ、すなわち結論の正しさを保証する。
エンシャーの型と論理
イランの学校作文は、作文一般と書く教育を表す「エンシャー」と呼ばれる。
主に四つの主題を扱う。① 自然現象、② 社会と道徳、③ 宗教、④ 国家
エンシャーの型
序論 主題の背景
本論 主題を説明する三段落
細かな主題群の三つの展開、三つの具体例など
結論 全体をまとめ、ことわざ・詩の一節・神への感謝のいずれかで結ぶ。
エンシャーは、序論で比喩によって主題を表現し、本論では比喩に関連づけて主題の内容を三つに区切って説明した後、結論で簡単に本文の内容をまとめて、作文のメッセージを的確に表現する、ことわざ、詩や聖典の一節、または神への感謝のいずれかの結びの言葉で締めくくる。
決められた結論へ向かう旅〜 真理と規範を伝える結びの言葉
「結論を出さずに、あるいは直接的な言い方を避けて、メッセージを伝えることが重要。」とされる。ことわざや詩の一節を結びに置くことが効果的という。揺るぎない「真理」を示すものと受けとられている。期待通りの道徳的・宗教的に正しい結論に落ち着くことが重視される。
エンシャーの歴史 〜声の文化から文字の文化へ
イランでは書くよりも話すこと、つまり文字の文化よりも声の文化が伝統的に重視されてきた。イスラームの聖典であるコーランも暗誦されることを前提にしている。
イスラームの論証の形
- 信仰の根幹に関わる神の存在の証明。
- 神の存在を受け入れた後で諸法令に服従しなければならない主張の論証形式。
- 法学者が法の解釈を行うための論証方法。
論拠と根拠になるのは、絶対的な規範の根拠である聖典コーランである。
西洋を中心とした現代の多くの国で重視されている「論証すること」は、イランの作文には馴染まない。神の為したこの世界のことがらはもはや議論する必要もなく個人が変えることもできない客観的な真理として存在している。もはや証明する必要はないからである。
社会の論理 〜日本の感想文と共感
社会領域のレトリックで重視されるのは社会の構成員から「共感されるか否か」である。共同体を成り立たせる親切や慈悲、譲り合いといった「利他」の考えに基づく個々人の「善意」が社会領域の道徳を形成する。道徳形成の媒体となるのが「共感」である。
感想文の構造と論理
感想文の型
序論 書く対象の背景
本論 書き手の体験
結論 体験後の感想=体験から得られた書き手の成長と今後の心構え
感想文の定義:生活の中の直接の体験や、自己の見聞、読書、視聴したことについて、自分の感じたこと、思ったことを書き表した文章。
感想文の質を保証するのは「自分の生活や生き方とどう関わるのか」という視点を持つこと。
起承転結
もともと漢詩の構成法として日本に伝わった「起承転結」は、物語のレトリックと受け止められているが、感想文にも効果的である。
共感と社会秩序の維持
感想文で期待されているのは個人の体験・感情・生き方を社会の構成員である他者と共有しうる「共通感覚」として表現することである。
獲得された道徳感は社会生活のあらゆる場面で発揮され、社会秩序の維持に貢献する。
他者になったつもりで感じ、他者の意を汲み取って、自らの身の振り方を考える思考法である。
意見文と小論文 〜共同体の内と外の思考法
感想文と違い、「意見文」と「小論文」は、いずれも「論証」の形式である。
意見文
自己の主張の正しさを論証して他者を説得するよりも、他者の意見への配慮を通して自己の考えを深めるためのものとされる。
意見文の型
序論 主張
本論 主張を支持する二つの根拠
主張への反論(「だが」、「しかし」)←他者への配慮
結論 主張への反論の反駁(「それでもやはり」)+主張の正しさの確認
自己の主張のみで押し通さず異なる意見へ配慮すること、すなわち他者への配慮を示すことである。
小論文
主張の論証が求められており、社会問題を複雑なまま受けとめる知性と切実性が要求される。結論を分かりやすいきれい事にしたり感情的な問題にしたりすると、小論文としては不合格である。
小論文の書き方の基本パターン
前提:テーマの確認と共有
- 常識論・一般的な見方の確認
- [ 常識論に関する ]違和感を「でも〜」という文脈で掘り起こす=別の角度から見る
- 現実を多面的に見ることによって違和感の根拠を得る
意見文が身近な問題を自己と他者の観点から考える共同体の中の議論の作法であるのに対して、小論文は社会や経済の構造と理論を通して共同体の外側からものを見る。初等・中等教育で身につけた感想文の思考法を「社会的なスキル」として、受験と高等教育で身につけた小論文の思考法は、「技術的なスキル」として用いる。
社会領域の思考法と日本の強み
日本の「感想文」は、心情を読み取る物語の読解とセットになって、他者の五感を自己のもののごとく取り込み感じることで、他者の期待を理解し、その期待に応える行為を志向させる。
感想文は状況によって複雑に変化していく人間の心情と、場を構成する人間と自然と社会環境の関係を読み取って反応できる共感力を鍛え、子どもを社会化する。
状況の変化に柔軟に対応しながら、譲り合う「利他」の精神が道徳の中核を成し、社会秩序が形成・保持される。
この強みは諸刃の剣となって、決断力の欠如という形で重要な局面で弱みになると批判されてきた。
しかし、複雑に原因が絡み合い予測不可能性が高まった二十一世紀の世界においては、この慎重な態度こそが想定外のリスクを軽減し、大きな間違いを起こさず柔軟に対処できる賢明な判断の方法になりつつある。
第三章 なぜ他者の思考を非論理的だと感じるのか
「自己の主張」の直線的な論証(経済)とは相容れない論理
経済領域から見た政治の論理
結論までの手続きが多く時間がかかりすぎる。出された問いには、ストレートに答えること、その答えの正しさを証拠づけて力強く論証し読み手を説得することがエッセイの目的である。
経済領域からみた法技術の論理
法技術の結論は、聖典・ことわざなどによって個人の外から与えられるものであるのに対して、経済領域のエッセイでは、個人が目的(主張)を決め、経験的ななデータを選択して効果的に論証する。
経済領域から見た社会の論理
「意見/主張」と「事実」を明確に分けていないように見える。常識をなぞるような感想や感じたままを綴っただけの生の感情の提示には面白みを感じることができない。
弁証法の「手続き」(政治)とは相容れない論理
政治領域から見た経済の論理
決定において間違いを起こしやすい短慮の議論の手続きに映る。結論を先に決めてしまって、結論に都合のよい材料を後づけで集めた政策を押し通して、失敗した例が数多く報告されている。
政治領域においては、効率性は問題にならず、勝つためには持てる限りの資源と時間をつぎ込まなければならない。手続きを遵守して審議に時間をかけること、あらゆる方面から可能性を吟味して「断定」を避け、慎重に答えを導くことに価値が見出されている。
政治領域から見た法技術の論理
自由の権利の侵害とみなされる。フランスでは、憲法ですら状況に応じて弁証法的に「変えていく」ことが重要である。
ディセルタシオンにおいては、「正しい答え」を出すことより、「正しい問い方」の方が重要である。
フランス革命が目指したのは、まさに宗教の統治からの人間の解放だった。
政治領域から見た社会の論理
社会領域の思考表現法は凡庸かつ学問的厳密性に欠ける子どもっぽい議論に映る。
日本の「意見文」も、反論への徹底した反駁が論証によって行われないため、不完全な論証、そして中途半端な議論に映る。
「ひとつに決まる結論」(法技術)とは相容れない論理
法技術領域から見た経済と政治の論理
「私は・・と考える。なぜならば・・」というエッセイの論理は、個人主義的で社会全体の秩序にとって危険であり、真理を保証しない。
法技術領域から見ると、政治領域の弁証法も真理を保証せず、非論理的である。絶対的な真理のもとでは、弁証法は意味を持たない。
法技術領域から見た社会の論理
経験的知識から導かれる個人の感情と、体系的な知識から導かれる普遍化された知恵のいずれを重視するかにより、二つの論理は違いを見せる。
エンシャーの結論となる結びのことわざや詩の一節が、感想文においては個人の感想で結ばれる。
他者への共感(社会)とは相容れない論理
社会領域から見た経済の論理
自己の主張のみを一方的に述べるエッセイは、多様な意見や価値観を持つ他者への配慮に欠ける。
社会領域から見た政治の論理
社会領域の「起ー承ー転ー結」の型は、ディセルタシオンの「正ー反ー合」に理解と興味を示す。しかし、「合」と「転」の違いは、「合」が「正」と「反」を総合して結論に影響を与えるのに対して、「起ー承ー転ー結」の「転」は、基本的には直接影響を与えない。「起承転結」は、文学的な文章の構成法として役に立つが、人々を説得するための言論には不向きである。感想文はもちろん、意見文も論証を目的としていない。
社会領域から見た法技術の論理
エンシャーは、児童生徒を型に押し込め、子どもらしい感情や学びのあり方を阻害するものと映る。感想文は、型にはめる教育から子どもの解放が目的である。人間を自然の一部として見る社会領域の自然観においては、子どもは最も自然に近い完全な存在であると受けとめられているため、社会が押し付ける概念や理念に縛りつけてはならない。
終章 多元的思考 〜価値を選び取り豊に生きる思考法
論理的思考とは何か
この問いに「論理的思考は目的に応じて形を変えて存在する」と答える。領域ごとに異なる目的を達成するために最も適した思考法が存在する。
経済領域では利益の追求が、政治領域では公共の利益の追求、法技術領域では真理の保持、社会領域では共感を通じた道徳心の涵養が優先され、それらの目的に合った、論理と思考法が選ばれ実際に使われる。
多元的思考の時代
何らかの問題の解決を考える時、解決にかかる費用や時間を優先させるのか、コストが高くついても問題に関わる人々の利益を最大限に考えるのか、規範やイデオロギーの遵守を優先させるのか、それとも共同体のつながりや存続を重視するのか。それぞれの領域には、問題を解決するための論理的な手続きと思考法があるため、どの領域を優先させて考えるのかを決定した後は、それに見合った思考法を技術として使うことができる。
どの国においても四つの領域があり、人々は日常の判断においてそれら四つの領域の間をスイッチしたり、ザッピングして見比べたりしながら、四領域の区分をあまり意識しないまま選択を行なっている。だからこそ、四つの領域を理解し意識することが大切になる。
渡邉雅子(わたなべ まさこ)
コロンビア大学大学院博士課程修了.Ph. D. (博士・社会学).
現在─名古屋大学大学院教育発達科学研究科教授.
専攻─知識社会学,比較教育,比較文化.
著書─『「論理的思考」の文化的基盤──4つの思考表現スタイル』(岩波書店,2023年),『「論理的思考」の社会的構築──フランスの思考表現スタイルと言葉の教育』(岩波書店,2021年),『納得の構造──日米初等教育に見る思考表現のスタイル』(東洋館出版社,2004年)
編著―『叙述のスタイルと歴史教育──教授法と教科書の国際比較』(三元社,2003年)
論文―“Typology of Abilities Tested in University Entrance Examinations : Comparisons of the United States, Japan, Iran and France,” Comparative Sociology, 14(1), 2015, pp. 79-101 など.