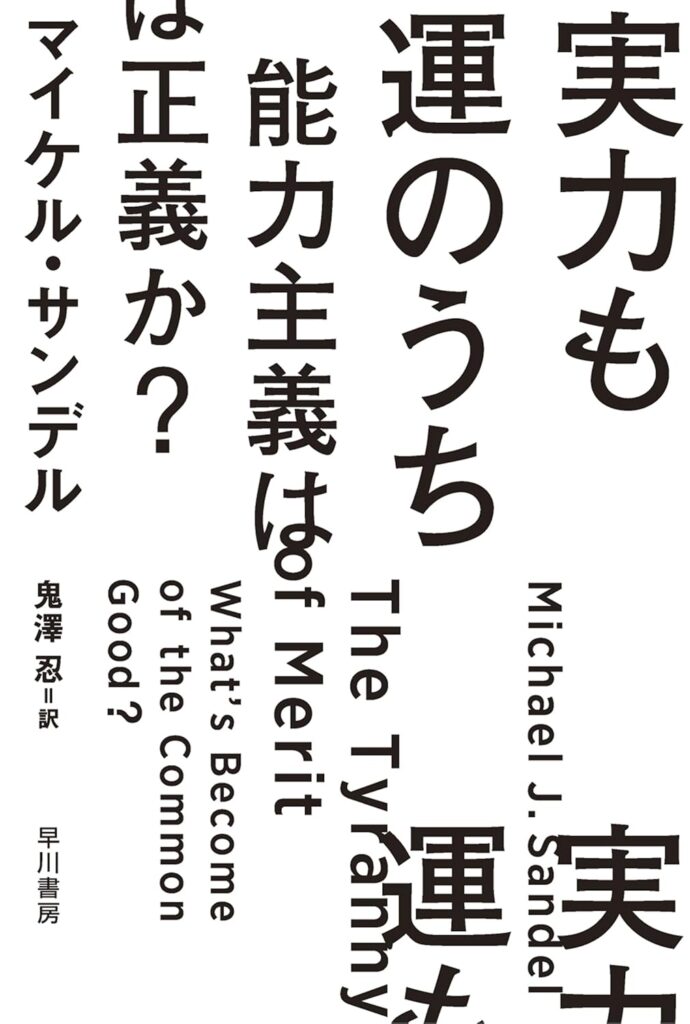2016年、不平等の高まりと文化的な敵意のせいで、怒れるポピュリストによる反動が生じ、ドナルド・トランプが大統領に当選した。
高学歴のエリートは成功を自分の手柄と考え、多くの労働者は成功者に見下されていると感じやすくなる。
2020年に、民主党のジョー・バイデンが36年ぶりにアイビーリーグ(アメリカ東部の名門大学グループ)の大学の学位を持たない民主党大統領候補となった。
大学入試の倫理学
アメリカの大学入試においてお金が物を言うのはありきたりのことであり、多くの大学が卒業生や多額の寄付者の子供に特別な配慮を払う点に顕著に現れている。
アイビーリーグの学生の2/3あまりが、所得規模で上位20%の家庭の出身。ブリンストン大学とイエール大学では、国全体の上位1%出身の学生の方が、下位60%出身の学生より多い。
不平等な社会で頂点に立つ人々は、自分の成功は道徳的に正当なものだと思い込みたがる。能力主義の社会において、勝者は自らの才能と努力によって成功を勝ち取ったと信じなければならない。
勝者と敗者
ポピュリストの不満の診断
第一の診断
人種的・民族的・性的な多様性の高まりへの反発。トランプを支持する労働者階級の白人男性有権者が対象。
第二の診断
グローバリゼーションとテクノロジーの時代の急速な変化がもたらした困惑と混乱。仕事は低賃金の国々に外注されたり、ロボットに任されたりしている。
やればできる
労働者階級と中流階級の多くの有権者がエリートに感じている怒りを駆り立てるものは不平等の拡大。
最も裕福な1%のアメリカ人の収入の合計は、下位半分のアメリカ人の収入全合計より多い。所得規模で下位1/5に生まれた人々のうち、上位1/5に達するのは、だいたい1/20人に過ぎない。
自力で貧困から脱出できると信じているアメリカ人は70%、ヨーロッパ人は35%にすぎない。
⇨勤勉で才能があれば誰もが出世できるというアメリカ人の信念は、もはや現実にそぐわない。
ドイツでは、成功のためには努力が肝心と考える人はやっと半数で、フランス人では四人に一人にすぎない。
アメリカに、ヨーロッパの社会民主主義国ほど寛大な社会保障制度がない理由は、ここにあるかもしれない。
能力主義の倫理
能力主義の倫理は勝者の間にはおごりを、敗者の間には屈辱と怒りを生み出す。
「やればできる」という考え方は、人を元気づける面と不愉快にさせる面がある。出世できなかった人々は、責任は全て自分にあると感じる。能力主義は目指すべき理想ではなく、社会的軋轢を招く原因だった。
偉大なのは善だから 〜能力の道徳の簡単な歴史〜
能力主義の理想は個人の責任という概念を極めて重視する。
聖書的な物の見方の2つの特徴が、現代的な能力主義を暗示している。1つは、人間の主体性の強調。もう1つは不運に見舞われた人に対する厳しさだ。神は、人間の善に褒美を与え、罪を罰する。神は、自分の好き勝手ではなく、人々の功績に応じてそれを行う。これもまた能力主義的考え方だ。苦難は罪を犯したしるしだという想定である。
ルターの反能力主義
神の恩寵をめぐるルターの厳格な教養は、断固たる反能力主義だった。それは、善行による救済を拒絶し、人間の自由すなわち自助の余地を残さなかった。
ジャン・カルヴァンも救済とは神の恩寵の問題であり、人間の能力や功罪によって決まるものではないと考えた。
繁栄の福音
この社会では、アメリカン・ドリームを支えるのは幸運ではなく多大な努力であるはずだと言われている。
アメリカのキリスト教徒の1/3近くが「神にお金を寄付すれば、神はさらに多くのお金で祝福してくれる」という見解を支持。61%が「神は人々が裕福になることを望んでいる」と信じている。「有徳な人々は十分な報酬を得る一方、邪な人々は結局は失敗するはず」=「自らの運命に対する個人の責任」を強調する。
健康と個人責任
ホールフーズ創業者のジョン・マッキーはウォール・ストリート・ジャーナル紙に論評を寄せ「健康障害の犠牲となっている人々の多くが自業自得」と主張。
我々の医療問題の多くは自ら招いたものだ。アメリカ人の2/3は太り過ぎで、1/3は肥満体だ。医療費全体の約70%を占める死を招く病〜心臓病、がん、脳卒中、糖尿病、肥満〜は、適切な食事、運動、禁煙、最小限のアルコール消費、その他の健康的ライフスタイルを通じて、ほとんど防げる。
能力主義に対する摂理主義
リベラル派や進歩主義者、なかでも平等にこだわる人々は、金持ちが金持ちなのは貧しい人々よりもそれにふさわしいからだという主義に反対する。平等主義のリベラル派は富の偶然性を強調する。人格や徳性に劣らず幸運や環境に依存する。勝者と敗者を分ける要因の多くは恣意的なものだ。
出世のレトリック
懸命に努力し、ルールに従って行動する人々は、才能と夢が許すかぎりの出世に値するという保証。
能力主義的倫理
成功は幸運や恩寵の問題ではなく、自分自身の努力と頑張りによって獲得される。権力や名声を自らの力で手にしたなら、私はそれに相応しい。成功は美徳のしるしで、私の豊さは私が当然受け取るべきものだ。
責任のレトリック
個人の責任を拡張する考え方は能力主義的な想定が働いている。自分の運命への自己責任が徹底されればされるほど、自分の人生の成り行きに関して称賛されたり非難されたりするのがますます当然のこととなる。
コミュニティが手を差し伸べるのは、その人の不幸が本人の落ち度ではない場合に限られる。
クリントンの就任演説:「全ての国民にさらなる機会を与え、いっそうの責任を果たしてもらいましょう。自分は何もせずに政府や同胞に期待するという悪しき習慣を断つべきときです。」
ドナルド・トランプ:才能と努力の許すかぎり出世できるという信念を語っていない。
ポピュリストの反発
底辺から浮かび上がれなかったり、沈まないようもがいている人々にとって、出世のレトリックは将来を約束するどころか自分たちをあざ笑うものだった。
トランプに1票投じた人たちには、ヒラリー・クリントンの能力主義の呪文がそんなふうに聞こえたのかもしれない。
学歴偏重主義 〜容認されている最後の偏見〜
学歴が武器となる現象は、能力や功績がいかにして一種の専制となりうるかを示すものだ。
2000年代にかけての主流派政党は、教育こそ、不平等、賃金の停滞、製造業の雇用喪失への対策の要であるとした。ビル・クリントンは、「何を手にできるかは、何を学べるかにかかっている。」と表現した。
フランクは、不平等の原因は主として教育の失敗だとする見方に疑問を呈した。真の問題は、労働者の権力が足りないということであり、労働者の知性が足りないということではない。
他人を見下すエリート
人種差別や性差別が嫌われている時代にあって、学歴偏重主義は容認されている最後の偏見なのだ。さらに、彼らは低学歴者に対する否定的態度については非を認めようとしない。
調査で、大学教育を受けたものは、教育水準の低い人々に対する偏見が、その他の不利な立場にある集団への偏見よりも大きいことがわかった。
エリートたちは、学業成績が悪いのは個人の努力不足であり、個人の力ではどうにもならない要因によるものではないと考えている。
学歴の低い人々に不利なこうした評価を学歴の低い者自身が、それを共有し、自信を大きく失わせている。
学位による統治
アメリカでは、労働人口の約半数が、肉体労働、サービス業、事務職として定義される労働者階級の仕事に従事している。ところが、当選する前にこうした仕事に就いていた者は、下院議員の2%にも満たない。州議会では、労働者階級の出身者はわずか3%にすぎない。
非大卒者が政府にほとんどいないという状況は、能力主義時代の所産だ。
優れた統治のために必要なのは、実践知と市民的美徳、つまり共通善について熟考し、それを効率よく推進する能力である。
洞察力や道徳的人格を含む政治的判断能力と、標準テストで高得点をとり、名門大学に合格する能力とは、ほとんど関係ない。「最も優秀な人材」は、学歴で劣るよりも同胞よりも優れた統治ができるという考え方は、能力主義的なおごりが生んだ神話なのだ。
成功の倫理学
能力主義vs貴族社会
貴族社会では、貴族に生まれた者は裕福で、農民に生まれた者は貧しい。一方、能力主義社会では、所得と資産の不平等は、世襲特権ではなく、人々が才能と努力によって獲得したものの帰結である。
能力主義社会において貧しいことは自信喪失につながる。貴族社会で農民に生まれれば生活は厳しいだろう。だが、自分の責任だと考えて苦しむことはない。
能力主義再考
現在、人類史上初めて、身分の低い者は自尊心を巧みに支えられるものを失っている。
教育水準の低い階級が、能力主義的エリートに対してポピュリストの反乱を起こしたのが、アメリカがトランプを大統領に選んだことである。
能力主義が完全に実現しさえすれば、その社会は正義にかなうという主張はいささか疑わしい。
努力が大切であるとはいえ、勤勉なだけで成功が手に入ることは滅多にない。努力が全てではないのである。成功は、才能と努力の合成物であり、その絡まりを解くのは容易ではない。圧倒的アメリカ人(約77%)は、懸命に働く気があれば、ほとんどの人は成功できると信じている。
能力主義に代わる2つの考え方
自由主義リベラリズム
オーストリア生まれの経済哲学者、フリードリヒ・A・ハイエク
自由と両立しうる唯一の平等は、法の下における純粋に形式的な全国民の平等だと主張する。「特定の個人の可能性に関わるあらゆる条件」を国家がコントロールする必要がある。功績と価値をはっきり区別し、経済的報酬を過度に道徳化するのは誤りだとしている。社会が評価してくれる才能を持っていることは、自分の手柄ではなく、道徳的には偶然のことであり、運の問題だとする。
福祉国家リベラリズム(平等主義リベラリズム)
アメリカの著名な政治哲学者、ジョン・ロールズ
階級の影響を完全に埋め合わせる制度でさえ、正義にかなう社会を生み出すことはないと主張する。真の機会均等を実現した社会でさえ、必ずしも正義にかなう社会ではない。
成功者が獲得したものを、彼らほど運に恵まれていない人々と分かち合うようにさせる。
市場価値vs道徳的価値
市場価値は道徳的功績を反映するという考え方への最も手厳しい批判は、新古典派経済学の創始者の1人、フランク・ナイトにとってなされた。
生産的貢献は倫理的な意義をほとんど、あるいは全く持ちえない。才能を持っていることは自分の手柄とは言いがたい。
人々が消費者の好みに応えることで稼ぐお金は、功績や道徳的な手柄を反映しているという想定は誤りだ。
「正」は「善」に先立つ
「正」(社会全体を律する義務と権利の枠組み)は「善」(その枠組みの内部で人々が追求する美徳や良き生に関する様々な概念)に先立つ。
生まれた当初から与えられている自然資産や、人生の初期に才能を育んでくれる偶然の状況は、道徳的観点からすると恣意的なものだ。
とりわけアメリカにおける現代の社会保険制度が、正義にかなう社会というロールズの構想に沿っていないことは間違いない。
労働を承認する
グローバリゼーション時代は高学歴者に豊な報酬をもたらしたが、ほとんどの一般労働者には何ももたらしていない。
絶望死
アメリカの労働者の意欲喪失を最も切実に表すのは、絶望死の増加だ。この100年で初めて、アメリカ人の平均寿命は3年連続で縮んだ。原因は、自殺、薬物の過剰摂取、アルコール性肝臓疾患などによる死亡の蔓延である。とりわけ中年の白人男性に多く見られる。
絶望死の増加の大部分は、学士号を持たない人々の間で起きている。4年制大学の学位を持つ人はほぼ無関係であり、最も危険にさらされているのは学位を持たない人である。学歴によって死亡率に大きな差がある。
怒りの源
ドナルド・トランプが善戦したのは、絶望死の比率が高い地域だった。
テレビ番組に登場するブルーカラーの父親は無能で愚鈍な物笑いの種として描かれ、有能な賢明な妻に支配されていることが多い。
人種隔離制度がなくなると、貧しい白人たちにとっては「自分よりもっと暮らし向きが悪く、もっとさげすまれている人がいるという気休め」がなくなった。
アメリカン・ドリーム実現のチャンスを列に並んで辛抱強く待っていると信じていた彼らは、前方の割り込みに気づいた。割り込んできたのは黒人、女性、移民、難民である。
労働の尊厳を回復する
彼らが直面し、遅れたのは、時代から取り残されることだ。失業の痛みは、たんに失職により収入を絶たれることではなく、共通善に貢献する機会を奪われることだ。
貢献の真の価値は、受け取る賃金では測れない。我々が人間として最も充実するのは共通善に貢献し、その貢献によって同胞である市民から評価されるときだ。
2つの政治方針案
- 低賃金労働者への賃金補助
- 経済の金融化の再編
金融は、いかに好調であっても、それ自体は生産的でない。
給与税を引き下げるか撤廃し、代わりに消費と資産と金融取引に課税して、税収を増やす。
結論 〜能力と共通善〜
社会の幸福は、団結と連帯を土台とし、高いレベルの一般教養の存在は不可欠。
出世しようとしまいが、尊厳と文化のある生活を送ることができなければならない。
自分だけの力で身を立て、生きているのではないこと、才能を認めてくれる社会に生まれたのは幸運のおかげで、自分の手柄ではないことを認めなくてはならない。
「神の恩寵か、出自の偶然か、運命の神秘がなかったら、私もああなっていた。」
マイケル・サンデル (Michael J. Sandel)
1953 年生まれ。ハーバード大学教授。専門は政治哲学。ブランダイス大学を卒業後、オックスフォード大学にて博士号取得。2002 年から2005 年にかけて大統領生命倫理評議委員。1980 年代のリベラル=コミュニタリアン闘争で脚光を浴びて以来、コミュニタリアニズム(共同体主義)の代表的論者として知られる。類まれなる講義の名手としても著名で、ハーバード大学の学部科目“Justice(正義)”は延べ14,000 人を超す履修者数を記録。あまりの人気ぶりに、同大は建学以来初めて講義をテレビ番組として一般公開することを決定。日本ではNHK 教育テレビ(現E テレ)で「ハーバード白熱教室」として放送された。著書『これからの「正義」の話をしよう』(ハヤカワ・ノンフィクション文庫)は世界的ベストセラーとなり日本でも累計100 万部を突破。