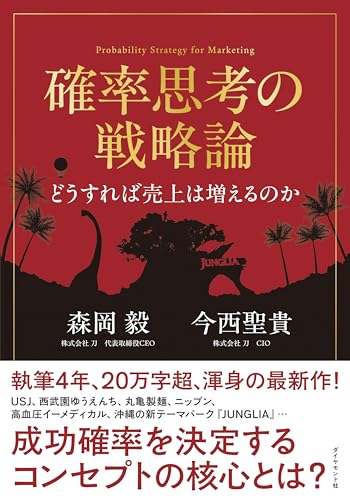「お客さんをもっと増やしたい。どうすればいいの!?」
自社ブランドが選ばれる確率をどうやって増やすのか?その最大の鍵となるのは「コンセプト」。「コンセプト」こそが人に選んでもらうための最大の変数である。
最初にお店のブランドのコンセプトを強化しないとお客さんは増えない。
「プレファレンス」に集中せよ
プレファレンス:その候補に割り振られた確率。そのブランドがもつ相対的な好意度。
1) 脳はブランドで選んでいる
売れるためには「プロダクト(製品・サービス)」よりもブランドの方がずっと重要で、プロダクトは大切だがブランドをつくるための手段に過ぎない。ブランドがまず選ばれないことには消費者の脳はプロダクトには辿り着かない。
[3つの脳の構造的な特徴]
- 最初に、自分にとって重要か重要でないかの判断をする。「カテゴリーの選択」
- 次に、できるだけ大きなところから選択しようとする。「ブランドの選択」
- 最後に、ランダムに選択する。「プロダクトの選択」
2) 脳はランダムに選んでいる:消費者による選択がランダムになされている
どの車を買うか、どのコンビニに行くか、どの旅行先に行くか、どのレストランで食べるか等。ほとんどのカテゴリーでこのランダムの法則が確認されている。
3) 成功が成功を呼ぶ
ランダムに結果出る「ポアソン分布」→ある試行結果が次の施行確率に影響を及ぼす「ガンマ分布」:一旦、話題になると有名になって、選ばれる確率がどんどん上がりブレイクする。
成功が成功を呼ぶが、失敗は失敗を呼ぶこと。
4) 市場の本質はプレファレンスである
あるブランドが選ばれる確率は、個々人ではポアソン分布、市場全体ではガンマ分布、その両方が消費者のプレファレンスによって決定される。
5) マーケティング戦略の変数はたった3つしかない
〜 プレファレンス・認知・配荷 〜
競合(代替品)に対する相対的な好意度であるプレファレンスをいかに高めれれるか?ビジネスの成功はその一点にかかっている。自社の経営資源をそこにどれだけ集中できているか。
- 認知率:そのブランドを知っている確率
- 配荷率:商品が店頭に並べれれている確率
- プレファレンス:その商品に割り振られた確率。そのブランドがもつ相対的な好意度。
狭めるな!広げよ!
1) 広く浅く売るよりも、浅く深く売る方が効率が良い」という考え方は間違っている。
プレファレンスが大きい方が、浸透率も購入頻度も必ずセットで大きくなる。
WHO:誰を幸福にするのか?
WHAT:何を解決して幸福にするのか? この順番で考えるのが先。
HOW:便益を満たす方法論に過ぎないプロダクトはその後。
より広く売ることに必死になることが重要。
2) 「ターゲティングありき」という間違い
できるだけ広く売る方法ありきで考えるべき。なぜならその方が効率が良いから。
浸透率が高い方が、必ず購入頻度も高い。
ただし、限りある予算内でコアターゲットを絞り込むことは正しい。
突出した”キワモノ”の場合は、一時的にターゲティングが実現するが、いずれ代替可能となり、ランダムな選択を迫られる。
プレファレンスは、垂直方向ではなく、水平方向に広げることを基本戦略とした方が良い。
重心を衝け!
重心:目的を達成するために全てをかけて戦略的に集中すべき1点。
1) 重心の見つけ方
組織戦において、1つの目的に直結する戦略のリソース配分の焦点(優先順位)は、多くても3つ以内に絞り切る。
消費者の脳内にどのような競争優位なブランド・エクイティ(企業価値)を構築するのかという意図的な選択。つまり、どんなブランドをイメージしてもらいたいか。
ブランドポジショニングは、他との比較によって、相対的に決まる。
2) 消費者価値にポジショニングする
ブランド戦略を考える上で最重要なもの ⇨ 消費者理解(WHOを喜ばす価値あるもの)
ずっと深く消費者を理解していないと競争には勝てない。
本物の消費者理解とは、本人の自覚なしに消費者を支配している”本能”と、消費者の”購買行動”(カテゴリー、ブランドの選択)の因果関係を明瞭に解き明かすこと。
カテゴリーにおける消費者の選択の軸となる「価値」を、自社ブランドが他社よりも第一想起される確率を高めること。
3) ブランド・ポジショニングの重心を定めるフレームワーク
重心は、”集客”であることが多い。
- 強いConsumer Value(消費者価値):本能に刺さる深層心理において認識される。
- Company Edge(自社の強み)
- Competitive Defense(競合防御)
「コンセプト」とは何か?
マーケティング・コンセプトは「本能にぶっ刺す」ことが重要。
その対象について、脳内で認識された意味のことを、広い意味で「コンセプト」という。
バイアスを与件とし、消費者のブランドに対する認識を悪い方でなく、むしろ良い方向に誘導することができるようになるのではないか? = 「要するにこういうこと」”意味づけ”のこと。
強い「マーケティング・コンセプト」をつくる
あらかじめマーケティング・コンセプトを刷り込むことによって、その価値をより強く実感ささることができる。これを”コンセプチャル・セル効果”という。
例えば、同じパンでも食べる前により強いマーケティング・コンセプトで価値を想起させておけば、より美味しいと感じる。人間の知覚は、認識によって大きなバイアスを受ける。
あるブランドに対して消費者が頭の中で想起するイメージのこと。これを消費者の脳内に構築することが最も重要。
消費者を徹底的に理解し、その本能が強く欲するものに明確な仮説を持つ。その仮説を判断軸にして、ブランドに必要な戦略エクイティを選ぶ。
全集中して消費者の本能が発露する構造を見極めて、自分のブランドをその本能にぶっ刺すようにポジショニングする方法を考え続ける。
マーケティング・コンセプトの究極の目的は、中長期にわたって競争優位をつくる”価値”を、自ブランドの戦略エクイティとして構築すること。
ちゃんとした広告を作れば、広告出稿をして劇的に売り上げが伸びる可能性がある。広告とは、即効性をもって認知を上げ、売り上げを伸ばすために存在する。
強いコンセプトは消費者理解がすべて
消費者の「本能」と「行動」の因果関係を読み解いていく。
消費者は便利なものを欲しがるが、便利さだけを個別に欲しがっているわけでは決してない。便利さだけを買う消費者はいない。
1) 重要性の関門
自分にとって重要か?
2) 好意度の関門
好きか、嫌いか?
期待を上回ることが大切。
3) 納得性の関門
本当に大丈夫か?
- 便益は本当に手に入るのか?
- 価格は妥当なのか?
- 他のオプションと比べても良い選択なのか?
「後悔したくない。悔いを残したくない。」という感情。
文脈を操作せよ
人間は文脈で判断する生き物である。ある事実や特徴など、情報を脳がどのように価値判断するかは、実は設定された文脈によって決まっている。
早く判断したい消費者の脳は文脈の材料になる情報に飢えている。
1) 価値を高めるシーンを設定する。
例:「健康診断で、内臓脂肪が気になったりしませんか?」など脳を衝くシーン。
2) 消費者のインサイト(消費者の隠された事実)を衝く。
「ええっ!そうだったのか!」と驚くほどの新しい情報を与える。
3) 消費者の”眼鏡(=期待値)”を変える。
消費者の心が動く。消費者の心の奥にあるドロドロした感情をを知り、脳に強く実感させる。
森岡 毅
もりおかつよし:1972年生まれ。神戸大学経営学部卒業。96年、P&G入社。日本ヴィダルサスーンのブランドマネージャー、P&G世界本社で北米パンテーンのブランドマネージャー、ウエラジャパン副代表などの要職を歴任。2010年にユー・エス・ジェイ入社。高等数学を用いた独自の戦略理論を構築した「森岡メソッド」を開発。窮地にあったUSJに導入しわずか数年で再建。その使命完了後の17年、株式会社 刀を設立。「マーケティングとエンターテイメントで日本を元気に!」という大義を掲げ、成熟市場である外食産業や製麺パスタ関連業界、金融業界、観光業界など多岐にわたる業界・業種において抜群の実績を上げる。24年、イマーシブ・フォート東京をオープン。沖縄の新テーマパーク「JUNGLIA」の25年のオープンにも取り組む。